バリアフリーの「バリア(barrier)」は「障壁」で、身体障害のある方や高齢の方が社会活動を行う場合に障害となるものを指します。「フリー(free)」が「・・・のない」ですから、「バリアフリー」は「障壁を取り除く」ことになります。従って、「情報バリアフリー」とは、身体障害者でも支障なく情報通信を利用ができるようにすることを意味します。
【情報バリアフリーの例】
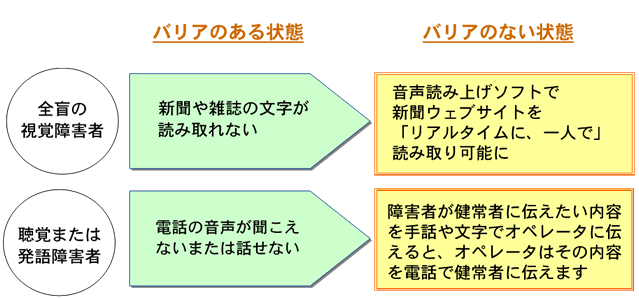
ページの先頭に戻る
情報化の進展に伴い、身体障害者の情報通信利用の必要性が増大しています。
「障害者利用円滑化法」及びこれに基づく施策では、身体上の障害がある方が情報通信の利用に支障が生じている場合、情報通信を実質的に利用可能となるように補完、代替、アクセスの改善を図る方針となっています。まさにこれは「情報バリアフリー」を意味しており、情報通信研究機構は情報バリアフリー社会の実現に向けて様々な支援を行います。
【関連用語】
- ・「アクセシビリティ(Accessibility)」
- バリアフリーと関連して「アクセシビリティ(Accessibility)」という言葉が良く使われます。これは、身体障害のある方や高齢の方も含めた人々の、交通・建物・機器・サービス等の「利用のしやすさ」を意味します。情報の入手しやすさは「情報アクセシビリティ」、ホームページの利用しやすさは「ウェブアクセシビリティ」といいます。
- ・「ユニバーサルデザイン」
- バリアフリーに近い言葉で、「ユニバーサルデザイン」があります。バリアフリーがもともと存在していたバリアを取り除くものであるのに対し、ユニバーサルデザインは特別な変更を加えることなしに、最初から全ての人に利用可能な設計をすることを意味しています。バリアフリーよりも進んだ概念ですが、ユニバーサルデザインで全てを実現することは出来ません。バリアフリー化により改善を進め、最終的にはユニバーサルデザインを目指すのも、現実的な取組み方法であると考えます。
ページの先頭に戻る