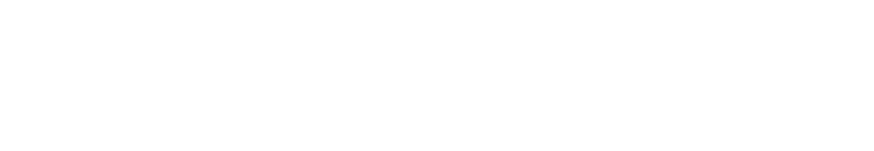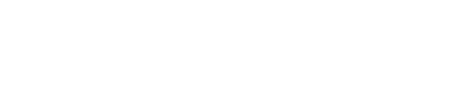- HOME
- 刊行物等
刊行物等/NICT NEWS & KARC FRONT etc.
*添付ファイルはpdfになります。
NICT NEWS
| 紹介内容 | 研究員名 | 掲載号 |
|---|---|---|
| 有機電気光学ポリマーが拓ひらく テラヘルツ波無線通信 | 梶 貴博 主任研究員 |
No.489(2021.No.5) |
| 単一光子計数法で探るナノ・量子の世界 | 井原 章之 研究員 |
No.476(2019.No.4) |
| ナノ技術が通信に新たな可能性を拓く | 大友 明 室長 |
No.455(2016.01) |
| 有機電気光学ポリマーの実用化に向けた研究開発 | 山田 俊樹 主任研究員 |
No.455(2016.01) |
| テラヘルツ有機デバイスの研究開発 -先端有機材料とデバイスの開発により高性能・小型光源を実現する- |
梶 貴博 主任研究員 |
No.455(2016.01) |
| 大気曝露に対してデリケートな試料を手軽に搬送 -可搬型超高真空試料搬送導入装置の開発- |
田中 秀吉 研究マネージャー |
No.450(2015.03) |
| 新紫外LEDが切り拓く未来 -ナノ光構造による光取出し効率の向上と実用化への取組み- |
井上 振一郎 主任研究員 |
No.439(2014.04) |
| 光情報通信技術のブレイクスルーがここに ナノICT研究の最前線 |
井上 振一郎 主任研究員 |
No.422(2012.11) |
| 原子分解能を有する溶液中動作型原子間力顕微鏡の開発 | 田中 秀吉 主任研究員 |
No.382(2009.07) |
| 生物学的な動きを情報通信分野に応用 | ペパー・フェルディナンド 主任研究員 | No.376(2009.01) |
| 非常に小さなエネルギーではたらく光デバイスをめざして | 栗原 一嘉 専攻研究員 |
No.373(2008.10) |
KARC FRONT
| 紹介内容 | 研究員名 | 掲載号 |
|---|---|---|
| 先端有機材料での「テラヘルツ波」発生 | 梶 貴博 主任研究員 |
Vol.32(2015.WINTER) |
| 超高真空SPMプロセスシステム | 田中 秀吉 研究マネージャー |
Vol.31(2015.SPRING) |
| 可搬型超高真空搬送装置 | 田中 秀吉 研究マネージャー |
Vol.31(2015.SPRING) |
| イオン性液体を屈折率マッチングオイルとした新規顕微ユニット | 山田 俊樹 主任研究員 |
Vol.31(2015.SPRING) |
| 有機色素分子を用いた電気光学光編長期の開発 〜情報通信を抜本的に高速・大容量化する〜 |
大友 明 室長 |
Vol.26(2013.SPRING) |
| 有機・シリコン融合フォトニクスによるオンチップ超高速光通信デバイス -最先端ナノ光デバイスが性能限界を打破する- | 井上 振一郎 主任研究員 |
Vol.26(2013.SPRING) |
| 有機色素のEO効果を向上させる分子設計法 〜有機EO色素の設計と評価〜 |
山田 俊樹 主任研究員 |
Vol.26(2013.SPRING) |
| ナノ・バイオ融合が見据える未来 | 田中 秀吉 研究マネージャー |
Vol.23(2012.SPRING) |
| 高度高塩菌から視覚機能をつくり出す | 笠井 克幸 主任研究員 |
Vol.23(2012.SPRING) |
| ナノ・バイオ融合領域での生体分子ICTデバイスを目指して | 春山 善洋 技術員 |
Vol.23(2012.SPRING) |
| 光科学技術における本格的なブレークスルーを追求し、光デバイスの未踏領域を切り拓く | 井上 振一郎 主任研究員 |
Vol.19(2010.WINTER) |
| 単一分子計測と光・分子デバイスへの展開 | 梶 貴博 専攻研究員 |
Vol.19(2010.WINTER) |
| 生体内での分子のブラウン運動を情報通信分野に応用 | ペパー・フェルディナンド 主任研究員 |
Vol.18(2010.SUMMER) |
| 光ナノ情報通信デバイスの研究開発 | 山本 和弘 専攻研究員 | Vol.17(2010.SPRING) |
| ”ナノとバイオの融合”が切り拓くKARCの新たな領域 | 大友 明 PM | Vol.15(2009.SUMMER) |
| 走査型プローブ顕微鏡の操作性を向上 | 田中 秀吉 主任研究員 | Vol.15(2009.SUMMER) |
| ソフトマターに基づくナノバイオICTデバイス研究 | 菊池 宏 専門研究員 | Vol.15(2009.SUMMER) |
| 産・官・学の共同研究で挑む、将来の高速・大容量・省エネ通信技術の創出 | 大友 明 PM | Vol.12(2008.SPRING) |
| 現状の不足部分を補うのではなく、今までになかったデバイスを分子から創る | 大友 明 PM | Vol.8(2007.NEW YEAR) |
| ナノスケール分子の相互認識能力によるボトムアップストラクチャリング | 田中 秀吉 主任研究員 | Vol.8(2007.NEW YEAR) |
| 非接触原子間力顕微鏡技術を確立し、有機分子の自己組織機能をナノスケールで制御する | 田中 秀吉 主任研究員 | Vol.5(2006.SPRING) |
| 次世代のコミュニケーション手段を支える有機・高分子材料の可能性に挑戦する | 横山 士吉 主任研究員 | Vol.4(2005.WINTER) |
その他新聞など
| 紹介内容 | 研究員名 | 掲載誌 |
|---|---|---|
| コンピューター 速度100倍 光信号に高速で変換 | 井上 振一郎 主任研究員 | 日経産業新聞(2013.10.23) |
| 深紫外線LEDの開発 | 井上 振一郎 主任研究員 | 日経産業新聞(2013.01.11) |
| 脳に似た進化回路実現 | ペパー・フェルディナンド 主任研究員 |
日本経済新聞他(2010.05) |
| 走査型プローブ顕微鏡の探針先端を3次元で 位置決めするシステムを開発 |
田中 秀吉 主任研究員 | 電波タイムズ(2009.02) |